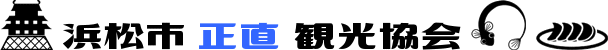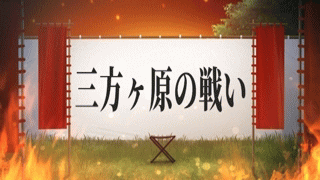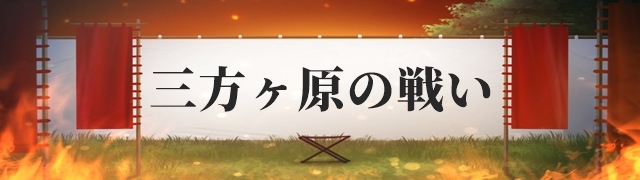
三方ヶ原の戦い決戦地は?
徳川家康最大の負け戦と言われている「三方ヶ原の戦い(みかたがはらのたたかい)」は、元亀3年12月22日(1573年1月25日)に、遠江国敷知郡の三方ヶ原(浜松市中央区三方原町近辺)で起こった武田信玄と徳川家康・織田信長の間で行われた戦い。
家康にとって負け戦だったということもあり、残っている記録も少なく、戦いの舞台となったのが、三方原台地ということ以外に詳しいことは分かっていない。
三方ヶ原の戦いの決戦地として有力視されているものに「小豆餅(あずきもち)説」「祝田(ほうだ)坂説」「本坂通(本坂街道)大山説」の3つの説があるが、どの説についても、明確に確定するような根拠にかけているため、現時点で 三方ヶ原の戦いの決戦地は分かっていない。
小豆餅(あずきもち)説
提唱者:旧参謀本部
旧参謀本部発行の日本戦史によると、三方ヶ原の戦いは現在の浜松市中央区小豆餅辺りであると記述されている。
武田軍が三方ヶ原に向かうためには、高低差がある三方原台地を上る必要があり、武田軍の一部は、現在の中央区有玉西町にある「大菩薩の坂」を上ったとされている。
坂を上っていくと、姫街道沿いに残るもっとも古い道標「最古の道標」がある。かつてここが姫街道と庄内道の分岐点であり、ここから二重坂を上ると三方原台地となる。三方原台地を上ると現在の小豆餅の北端に出る。
小豆餅説では、この辺りの武田軍が本陣を構え、対面する南側に徳川軍が本陣を構えたとされている。
現在に当てはめると、国道257号線上で両軍が向かい合い、武田軍が「デニーズ浜松葵東店」辺りに本陣を構え、徳川軍が「びっくりドンキー 浜松萩丘店」辺りに本陣を構えたということになる。
一方で、三方ヶ原の戦いの決戦地、小豆餅説には異論の声もある。
元々、武田軍は浜松城を落とすことが目的ではなかったため、浜松城を無視して三方原台地を抜けようとした。
家康にとって武田軍は正面からやりあいたくない相手ではあるが、武田軍の進軍を許すと後の戦況が不利になり出撃せざるを得ないという状況や、武田軍に無視されたことに家康が腹を立て出撃したのが三方ヶ原の戦いの始まりと言われている。
小豆餅が決戦地ということであれば、徳川軍が武田軍を待ち構えたということになり、正面からやりあうことを避けたい家康がとる行動と矛盾し、武田軍が無視という状況にも当てはまらない。
また、当時の家康は若く勇ましい武勇伝も残っているが、自らが先陣を切って敵陣に攻め込むタイプとは言えない。
三方ヶ原の戦いでは家康が武田軍の追手から「命からがら逃げた」と言われているが、家康が本陣を構えたとされる小豆餅の南側は浜松城からすぐ近く。
三方ヶ原の戦い以前の小競り合いでも撤退を繰り返してきている家康だが、三方ヶ原の戦いでは、戦況が厳しくても最後まで引くことなく前線で戦ったというのでなければ「命からがら逃げた」という状況は考えにくい。
祝田(ほうだ)坂説
提唱者:歴史学者 高柳光寿
歴史学者「高柳光寿」氏は、昭和33年発刊の著書「武田信玄の戦略(三方ヶ原の戦い)」の中で、三方ヶ原の戦いの決戦地は祝田坂(浜名区細江町)周辺であると発表した。
江戸時代、大久保彦左衛門が書いた「三河物語」の中に、「家康 浜松より三里において討ち出させたまひて」という記述から決戦地が祝田坂周辺であるとしている。
状況としては、武田軍は三方ヶ原を通過して三河方面に進むため祝田坂を下ろうとしていたとろを、徳川軍が背後から追撃しようとした。しかし、武田軍は坂を下る前に軍を反転し、祝田坂の南側 根洗町辺りに本陣を構え約25000の大軍で徳川軍を待ち構えていたとしている。
現在は道も舗装され、国道257号線 金指街道が祝田坂につながっているが、戦いの舞台となったとされるのは、西側の旧金指街道・旧祝田坂である。
今現在、三方ヶ原の戦いの決戦地として最も有力視されているのが「祝田坂説」ではないだろうか。
先にも記述したが、三方ヶ原の戦いは武田軍が浜松城を落とすことを目的としたのが始まりの戦いではない。
衝突場所が祝田坂ということであれば、先に話した通り、家康にとって出撃せざるを得ないという状況や、武田軍が無視して浜松を通過しようとしたことに腹を立てた家康が戦いを仕掛けるということに疑問は生じない。
また、戦いにおいて高所を陣取った方が有利という戦略上、家康が祝田坂を下っている最中の武田軍に攻撃を仕掛けようとすることは理にかなっている。
一部には、祝田(ほうだ)の坂を下ったところ「蜂前神社」周辺に武田軍が本陣を構えたという説もあるが、武田軍は25000人の大軍なので、当然この一帯は武田軍が陣取っていたであろうから、決戦地は祝田坂周辺ということで、坂の上・坂の下といったことは特に気になることではないと思われる。
本坂通(本坂街道)大山説
提唱者:鈴木千代松(三方原町の歴史研究家)
鈴木千代松氏が平成7年に発表した、著書「三方原の戦いの研究」によると、金指街道・祝田坂から西に約2Kmほど離れた「本坂街道」、現在の姫街道の大山付近ではないかと発表した。
根拠として、戦いが行われた地に何らかの遺跡が残るのは当然のこと。戦いの後を伝える慰霊碑は「おんころ様」「精鎮塚」の二つ以外見つかっていないことを挙げている。
武田軍の慰霊碑?おんころ様
大正時代の中頃までこの場所には「おんころ様」と呼ばれる「卒塔婆塔」があったとされる。
大正12年の関東大震災の余波で倒壊してしまったが、地元住民の話によると、今から約30年ほど前まで、現在の本坂通(姫街道)沿いの畑の中に「おんころ様」の跡を示す祠があったという。
卒塔婆(そとうば・そとば)とは、仏塔を意味するもので、一般的には「追善供養のために経文や題目などを書き、お墓の後ろに立てる塔の形をした縦長の木片」のことを言うが、この地にあったのは「卒塔婆塔」ということなので、お墓という認識で間違いはない。
誰のお墓でなんのために建てられたかは不明だが、「浜松御在城記」にある一文から、この卒塔婆は武田軍に関係があるものではないかと考えられている。
此合戦ノ時 甲州方(武田軍)小藩尾張重定四男 又八郎昌定 討死 三方原に塚を築く 卒塔婆を立候と信玄全書に見たり
簡単に言うと、武田軍の又八郎昌定は「自分が死んだらこの場所に卒塔婆を立ててほしい」という遺言を残し三方原の戦いで討死した。
このことから卒塔婆は、武田信玄が家臣の又八郎昌定の霊を弔うために建てたのではないかと推測できる。さらに、討死といっても戦場で徳川軍に討たれたのではなく、戦病死といわれているため、つまり、ここに武田軍の本陣があったのではないかという考えに至る。
徳川軍の慰霊碑?精鎮塚
「おんころ様」と向かい合う位置、浜松市中央区花川町を通る県道319号線沿いに、精鎮塚(しょうちんづか)がり、この場所が徳川本陣ではないかとしている。
現在、精鎮塚は三方原町の「本乗寺」というお寺に移動されたのだが、本乗寺の住職の祖先が三方ヶ原の戦いで戦死したことが分かっている。
三方原地域には精鎮塚が徳川軍の戦死者の墓を祀ったもという伝承が残っていることから、本乗寺 四代目住職が祖先の徳川軍の死者を弔うために精鎮塚を移動したのではないかと推測できる。
三方原で戦いが行われたのは事実であり、ここに何らかの遺跡が残るのは当然のこと。三方原台地で戦いの後を伝える慰霊碑は「おんころ様」「精鎮塚」の二つ以外見つかっていないことから、三方ヶ原の戦いの決戦地が「本坂通(本坂街道)大山説」というのが根拠とされる。