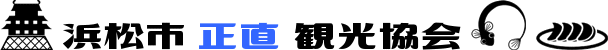2026年2月6日(木曜)浜名漁協の発表によると、深刻な不漁が続き昨年(2025年)は全面中止となった浜名湖・弁天島周辺の観光潮干狩りだが、2026年(令和8年)も漁獲量の回復の兆しは見られず、8年連続(通算11回目)の中止となることが決まった。
近年のアサリの漁獲量減少は深刻で、潮干狩りを開催するには程遠く、2009年の6007トンをピークに減少傾向が続き、2021年以降は「壊滅的」と表現する漁業関係者もいるほどの状況だ。
【アサリ漁獲量】
- 2025年:0トン
- 2024年:0.18トン(最盛期の2009年の3万分の1)
浜名漁協によると「浜名湖のアサリは挽回するには元種がなさすぎる」と話し、観光潮干狩りの中止に加え、今年は例年3月に解禁となり、一定ルールの元で認めていたアサリ漁を浜名湖全域で年間を通して全面禁止(漁業者を除く)とし、資源回復を目指す。
これまでも、観光潮干狩りの中止の他に、あさりの資源保護の取組として、漁師の1日の漁獲量の制限、休漁日、操業時間、採取対象の貝の大きさ、禁漁区などの規制や稚貝の湾内移動放流などが行われ、浜松市もアサリの資源回復に向けて、2025年度当初予算案に関連費340万円を計上し、人工稚貝と、すみかとなる海草のアマモの育成を支援することを決めるなど、様々な対策がとられているが、効果を感じることはできず、浜名湖の風物詩でもある潮干狩りは存亡の危機に立たされている。
浜名漁協の公式の発表ではないが、漁業関係者によると、潮干狩り再開の目安としては、最低でも2トン以上の漁獲量が必要と話す。
漁獲量減少の正確な原因は定かではないが「水温上昇によるクロダイの食害」「猛暑・異常気象などの気候変動」「観光客や漁師による乱獲」などの理由が挙げられているが、最も有力な説が「浜名湖の湾口工事による環境変化」といわれている。
【湾口工事による環境変化とは?】
浜名湖は、山と谷が作る入り江が砂州によって塞がれてできた「海跡湖」のため、海とつながる出口付近が浅く、湾の奥が深いという特殊な地形が特長だ。
アサリは浅い海域を好む性質があるため湖の入口辺りに多く生息していた。また、湖の入口辺りは湾の奥に流れ込む河川から供給される淡水が、湾入り口寄りの浅い場所で塩分濃度の高い海水と混じり合い、栄養も豊富で、水質がアサリの生息に適していた。
しかし、湾口の工事が進み、湖に外洋から潮が多量に入るようになったため、湾入口付近の塩分濃度が上昇してしまい、水質がアサリの生息に適さなくなってきた可能性があると考えられる。
「湾口工事による環境変化」が大きな理由であれば、もはや漁獲量の回復は困難を極め、もはや漁獲量の自然回復は絶望的、浜名湖の風物詩「潮干狩り」が無くなってしまう可能性もある。
いずれにしろ、漁獲量の減少は現在進行形の問題であり、これからも注視していく必要がある。